教育
在学生の声

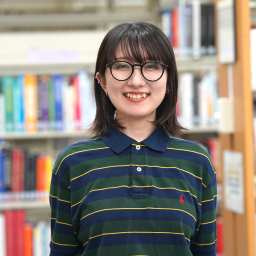
成毛 侑瑠樺
NARUGE Uruka 2021年4月入学
熊本県出身(志成館高等学院)
実現したい社会をつくるため
課題解決の手法を実践的に学ぶ
私が叡啓大学を選んだ理由は、実現したい社会をつくるための方法を学べると思ったからです。高校生の頃から子ども達が生きていていいと思える社会をつくるため、不登校の中高生やその保護者、教師向けの講演会やイベントを企画するなどのプロジェクトを実施してきました。しかし、継続的な変化を起こすことができませんでした。叡啓大学で学ぶことで、こうした状況を打破できるのではないかと考え入学しました。入学後は、システム思考やデザイン思考を用いて課題解決の手法を実践的に学びながら、自分自身の成長や活動につなげることができていると感じています。
「学生協働プロジェクト」を通して
今年2月、学生と企業が共同で取り組む「学生協働プロジェクト」に取り組みました。学生が有償の仕事として、企業の直面している本質的な課題を特定し、解決策の提案を行います。私たちのチームでは、課題解決演習(PBL)の授業で学んだ課題解決フレームワークを用いてプロジェクトを進めました。学んだ知識やスキルが実際のプロジェクトと結びついた時はとても感動しました。また、課題解決の一連の流れを授業で学んだため、プロジェクトを俯瞰的に見て構造化することや進むべき方向性を定める能力が身に付いていることに気がつきました。
さらに同じ熱量を持つチームでプロジェクトを進める意味や楽しさに気付きました。これまで、チームでの活動は、メンバーのやる気の差が出やすくもどかしさを感じていたため苦手意識を持っていました。しかし、「学生協働プロジェクト」の活動では、同じような熱量のメンバーが集まり、毎週ホワイトボードや付箋、miroなどを使って議論をしながらプロジェクトをやり遂げました。また、メンバー全員のキャラクターが違ったため、それぞれが自分の力を発揮できる得意分野を活かして協働しました。その中で、自分とは違う人たちが集まることで生まれるアイデアの面白さ、プロジェクトを推進させるスキルなどを学びました。
子どもたちが生きていていいと思える教育や社会のシステムづくり
将来の夢は、子どもたちが生きていていいと思えるような教育や社会のシステムづくり、社会の誰かが理不尽に不幸にならないような仕事をしたいです。例えば、学校支援に関わる教育系NPO法人や企業、企画やプロジェクトマネージメントに携わる仕事に興味があり、不登校向けのイベントや講演会、中学校での授業運営など今行っている活動の延長線上で働きたいと考えています。
(2024年6月)


